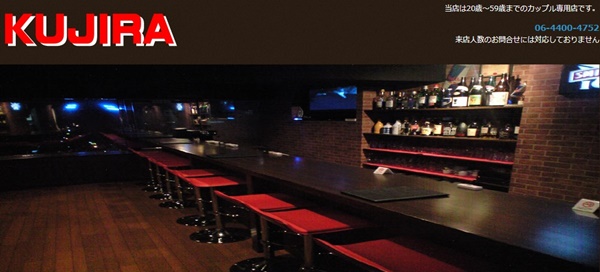外回りの営業職である私には、最も利用頻度が高いお店の形態が「コンビニ」である。
朝家を出ると、まずは「コンビニ」で眠気覚ましの缶コーヒーを手に取る。
顧客訪問の合間には、「コンビニ」で昼食を購入して、営業車の中で済ませる。
小腹が空いては「コンビニ」で間食を買って、一日の終わりに「コンビニ」のスイーツやアイスで自分をねぎらう。
なんとなく「コンビニ」に立ち寄り、なにかないかなと探している自分がいる。
実際にクレジットカードの明細を確認してみると、毎月40回程度の利用していた。

一方で、アラフォーにもなれば、気になるのは「健康」、「お金」、「仕事」、「家庭」。
これらの悩みは、多くの人が抱える共通のテーマだろう。
コンビニに行くのをやめてみれば、「お金」や「健康」といったことにはプラスになるのでは、つまりは、自分が抱える悩みの50%くらいは改善できるんじゃないかっていう思いに至り、まずは一か月の挑戦をしてみた。
この記事では、単純にコンビニに行くのをやめてみての体験談だけではなく、依存症とそのメカニズム、やめるための方法も記載している。
実際どうだったか含めて参考にしていただければ幸いである。
やめるきっかけ
遊ぶお金を工面したい
悲しいかな、私は世の中の大半の人がそうであるようにお小遣い制である。
(と思っていたけど、半数はお小遣い制ではないようなのね、、、)
そして、お小遣い制である限り、年収が多少上がろうがお小遣いの額が大幅に増えることはない。
我が家の夫婦間のパワーバランスが影響していることもあるけれど、子供関連の出費は年々増すばかりで、多少給料が上がってもお小遣いを上げてくれとは言いにくい。
そんな状況において、自由に使えるお金を増やす手っ取り早い方法は、、支出の削減となる。
もちろん、普通に生活をしていて困るようなお小遣いの額ではないのだけど、遊ぶとなると全然足らないのである。
コンビニでの一か月の支出を単純計算すれば(40回の利用として)、一回の平均利用額が300円であれば12,000円、500円で20,000円、700円で28,000円である。
(実際は、毎月15,000~20,000円程度をコンビニで利用していた)
15,000円コストカットできれば、飲みなら2回、女遊びなら1回の足しにはなるだろう。
さらに、2024年ぐらいからの値上げで、単純にコンビニ商品の単価が高い。
平成を生きてきた私からすれば、おにぎりや菓子パンは一個100~120円程度という感覚をもっているのだが、最近では、一個150円~200円程度なのではないか。
よくよく考えてみれば、現状の物価高を考えれば「適正価格」なのだろうが、私の「期待価格」と「実際の価格」にギャップが生じているのは事実である。
ということで、まずは一か月コンビニに行くのをやめる方針にした。
コンビニ依存症になっていないか
「コンビニ依存症」という病気があるのであれば、私は間違いなくコンビニ依存症であろう。
(実際にネットでは、コンビニ依存症という言葉が出てくる)
コンビニ依存症の明確な定義はないだろうが、以下のような特徴が挙げられる。
- コンビニで買い物をすることが癖となっている
- 特に用がなくてもコンビニに寄ってしまう
- 欲しくもない商品を買ってしまう
- コンビニに行かないと不安になる
みなさんも当てはまることはないだろうか。
私は、コンビニに行かないと不安になるわけではないが、とりあえず寄ってしまい、とりあえず何かを買ってしまうということは当てはまる。
特に仕事でのストレスを感じた際に、コンビニに行く回数が増える。
決めたこと
依存症のメカニズム
コンビニ依存症になっているのであれば、まずは、その原因を知ることが重要である。
依存症のメカニズムは、
- ある行為によって、脳の報酬系(ドーパミン)が刺激される
- 脳がその行為を「報酬」として認識し、報酬を求める回路が脳内にできる
- 脳がその行為を学習し、本人の意思とは関係なく繰り返すよう求める
- 繰り返されることで報酬を求める回路が強化される
- 刺激に対する耐性ができ、さらに強い刺激を求めるようになる
- 自分の意思ではやめられない状態になる
私の場合は、仕事でストレスを感じ、その間にコンビニで昼食や甘いものを買うという行為で、脳がコンビニに行くことでドーパミンを出しているのだと思われる。
そして、脳にその回路が出来てしまっているので、何かストレスを感じたときや、時間があるときなどに、脳が報酬を求めるために、コンビニになんとなく寄ってしまうのだと思われる。
マイルール
マイルールを設定する際には、依存症の克服のプロセスを参考にすることが効果的だ。
もちろん、強い買い物依存症であれば、専門家の助けも必要となるだろうが、そこまでではないので自力でできる範囲でだ。
- 現状を把握する
- コンビニに行くデメリットを書きだす
- コンビニに行かないメリットを書きだす
- 具体的なルールを作る
- コンビニに行かない仕組みを作る
- ストレスをため込まない
- 周囲に宣言する
マイルール
- 仕事関連以外では、コンビニに一切立ち寄らない
- 毎日の終わりに手帳に成果を記載する
期間の設定
行動に関わる習慣化の期間は、約1か月程度とされている。
毎日のルーティーンにしていくことで、一か月後にはそれが当たり前の行動となるわけだ。
なお、インキュベーターの法則というものもあって、それは行動心理学では、新しい習慣を身に着けるためには「21日間」継続させる必要があるらしい。
期間に関しては、様々言われているようだが、とりあえず、私はキリがよい1か月に設定した。